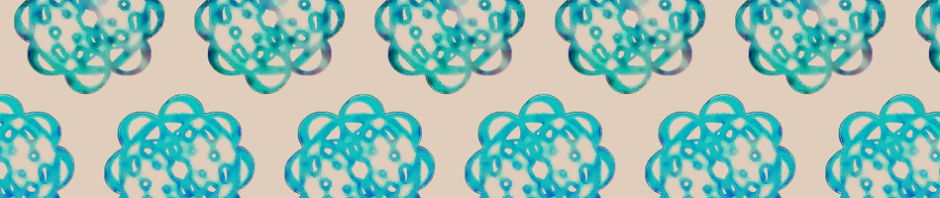泣きたい。
次第にはっきりとしてくる意識のなかで、ひどい虚脱感が輪をかけて苛んでくる。
頭の中で様々な言い訳が浮かぶが、どれも現実味はないし幼稚でばかげたものだ。そもそも何を納得させたいのかも分からない。
じっとりと滲む嫌な汗と、全身に広がる疲労感。
肺から追い出した息すら、まだ余韻を残しているように熱い気がして、またその熱と冷めた身体と思考のせいで一層惨めな気持ちになる。
まだ若く、少年と青年の境目にいる年頃には、自分の身体すら持て余すことがある。生理現象に逆らえないのは人間だからだし、思春期と括られる年齢特有の現象としては仕方のないこととは言え、自分には緊張感がなさすぎるのではないかと頭を抱えたくなってしまう。
神々の戦いやらに引っ張り出された。己で戦うと決めたのだから、それは責務であり任務だ。先の見えない世界だからこそ、己は捨てて任務を果たすべきだと言うのに。
スコールは凭れていた木から背中を離して、のろのろと衣服を整えながら、冴えてきた頭で水場の地図を思い浮かべる。
汚れた手を、一刻も早く洗い流したい。そしてさっさと眠って忘れてしまいたい、こんな愚かな夜のことなど。
見たくもない地面に残した劣情の名残が弱々しい月明かりで分からないことに慰められて、重い足取りで水場に向かおうとしたその時。
がさりと聞こえた葉擦れの音に、スコールは無意識に構えた。
同時にしまったと舌打ちする。熱に浮かされた頭で、武器を置いてきてしまっていたことに後悔したのも束の間、すぐに陽気な声が耳に届いた。
「おっかねえなー。
スコール、俺だよ」
「……ジタン。
何だ?」
すぐ脇の茂みからひょこりと覗かせた見慣れた顔に、正直、一番タチの悪い相手かもしれないと、少々気まずい思いを感じながら顔を逸らせて吐き捨てる。合わせられない視線に首を傾げて、ジタンは茂みの中なら出てきた。
「何ってこっちの台詞だろー?
交代で起きたらお前いないし、セシルに聞いても知らないって言うし、
その上ガンブレード置きっぱだし、何かあったのかと思って探しに来たんじゃねーか」
その制で見張りの交代をセシルに待ってもらっているのだとジタンは責めてくる。
それには絞り出すような声で悪いと告げた。スコールとしてはできれば今すぐにでもこの場を離れたいと言うのに。
「で。何してたんだよ?」
「関係ない」
「………」
ぴしゃりと言い捨てて追及を打ち切らせようとするが、当然納得いかないジタンはスコールの考えを読もうとでもするかのように凝視してくる。
「何もない。気にするな」
「気にするなったって……」
「もう戻る」
「………」
スコールは眼差しを無理矢理振り切る。
いつも無愛想な彼の態度に腹を立ても傷つきもしないが、ジタンの脇をすり抜けて行こうとするスコールに何かを感じたらしく、少しの間、彼がいた場所を見つめていた。
内心穏やかではないスコールが振り切るように踏み出した瞬間、彼の右手にするりとジタンの指が絡まった。指と指とを繋ぎ合わせるように握りしめられ、我知らず心臓が跳ねる。
意を決して見下ろしたスコールの視線の先で、彼は青い瞳を輝かせていた。
まるで、獲物を見つけた猫の目だ。
「次は俺にも声かけろよな」
含んだ声音が密やかな秘め事を連想させて、スコールは顔を真っ赤にした。
はたして、見透かされた愚かな振る舞いにか、眼前の仔猫の艶めいた誘いにかは定かではなかったが。