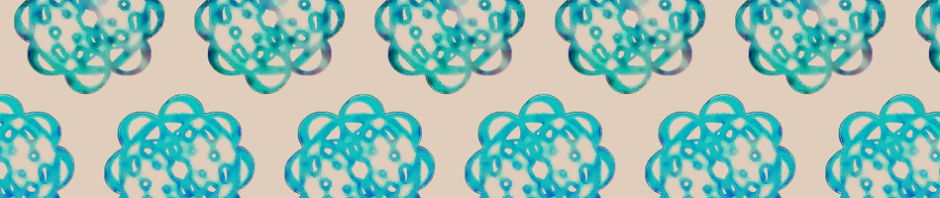1 実際に測ってみた
カインから真正面に見つめられたセシルの問いは呑気なものだった。
僕の顔に何かついてる? 首を傾げる幼なじみの不思議そうな視線には取り合わず、カインは彼の手に触れる。
「?」
これに一層の疑問の色を濃くしたセシルだったが、最初の答がないことでそれ以上の問いかけは無意味だと判断したらしい。
向かい合ったカインの左手が、するりとセシルの右手に絡まる。そして同じように反対の手も繋がれて、そっと握りしめられる。カインの視線は互いの手元に注がれていたが、こちらの反応を窺っている節がある。かと言って不快な感じはしない。
セシルは分からないまま、何となく絡んでくる彼の手を握り返した。
カインは少し時間をかけて、改めてセシルの顔を見返したようだった。
「?」
また変な間を置いた後、繋いだ手はそのままでカインは距離を一歩詰めてきた。
ひと一人分もなかった二人の距離はすっかりなくなり、カインはセシルの肩に顎を預けることができた。ただ、身体自体は拠ることはなく直立したままだったから、少し苦しいかも知れない。セシルは自然な成り行きで、彼がハグをしたいのだと結論した。
手を解いてカインの背中に回し、引き寄せる。自分も相手の肩に顎を乗せて――いやむしろ顎で肩を固定するように埋めた。
彼の体温を感じられるように時間をかけて抱擁を堪能し、セシルはこれまた自然な成り行きでカインから離れる。
間際に去りゆく頬に口付けを残していくことも忘れない。
「……」
「………」
そして、どちらのものとも言えない沈黙の後、カインの眉間に皺が刻まれる。
「……え! なに?」
「別に……何でもない」
「??」
急に表情が変わるのはさすがのセシルも驚いた様子で、最初より多くの疑問符を頭に浮かせながら幼なじみを観察する。
「何でもない。ホラ」
カインは彼の疑念の視線を手で振り払って、セシルの首に腕を回して引き寄せる勢いのついで、唇にキスを見舞う。
「帰るぞ」
きょとんと瞬きをするセシルに声をかけると、彼は納得いかない表情でありながら、うんと頷いてカインの隣に並ぶ。
すぐに始まるのは他愛もない学校での話やら、今日の夕食やら。
屈託のない笑い声を聞きながらカインは、思った以上に狭まっていた関係にひっそりと驚いていた。
.
.
.
.
.
2 思ったよりも長い
「それでね」
セシルはたまに、相手の都合を考えない会話をすることがある。大抵の人間は振り回されるが、慣れているカインはそれを上手に聞き流す事ができた。ただしその会話のなかに迷惑な提案が含まれている時は、少々厄介になるが。
「次の日曜は、朝五時に並ぼうと思うんだよね」
「大変だな」
「競争率高いからね。
でも、整理券貰っても抽選なんだって!」
「並んでも買えないのか」
呆れたような声を出すカインは、前述どおりほとんどを綺麗に聞き流している。
「そう! だから、一人より二人の方が確率上がるよね!」
「全くその通りだ」
思ってもいない生返事にそれらしい感情を流し込めるようになったのも、長年の付き合いの賜物だ。
「ありがとうカイン! 君ならわかってくれると思ったよ!」
セシルが何だか勝手に感動してくれているので、カインも鷹揚な態度を見せる。
「お前との付き合いも長いしな」
「うん! じゃあ一緒に頑張ろうね!」
あれ?
「なに?」
「何って、シュークリーム」
「シュークリーム??」
「うん。人気だから、朝五時に並ぼうね!」
ひとり得心顔で頷くセシルから、カインは置いてけぼりを喰らっている。つい足を止めてしまったカインをよそに、セシルは意気揚々と帰路を進んでいく。
「カインもさー、何だかんだ言って甘い物好きだよねー」
「お前と一緒にするな」
振り返る笑顔に渋面で答えると、セシルは思ったより離れてしまっていたことと、否定されたことに同時に驚いたようだった。
「えー、だって僕がお菓子食べてたら、横取りしてくるじゃない」
「…………横取りだ?」
「キスしてくるでしょ」
えー……
確かに、味見と称してキスを仕掛けることはよくある。
あるが、もしかして、すべて額面どおり受け取られていたのだろうか……
カインはふと、聞き流して落としていった単語を拾うように後ろを振り返るも、何だか長い道のりを望むような気持ちになった。
.
.
.
.
.
3 障害物撤去
寮に帰って夕食を摂ったふたりは、のんびりと課題を片付けていた。
「そう言えばさ」
部屋の背中側にいるセシルが、テキストを読む視線を動かさずに声を上げる。
カインが黙って続きを待つ中、かりかりと鉛筆を滑らせる音が数度行き交ったのみ。
「……なんなんだ」
しばらく後、問題集から顔を上げて呻くカインの呟きに、セシルは首を傾げる。
「ん? あ。そうそう。
明日さ、雨が降るんだってね」
「で?」
「ううん。それだけ」
「………」
あまり得意ではない数字の羅列を追っていたカインだったが、もとより興味の薄い分野のこと、余計な情報が入った途端、集中力が一気に霧散してしまった。
「ああっ、畜生」
「……どうしたのさ急に」
カインがばさばさとノートを振る音を咎めるように、それでも自分の手は休めないセシルに一瞬殺意を覚える。
「お前の制でやる気がなくなった」
「うわーひっどい責任転嫁だ」
そこでやっと鉛筆の音が止まり、セシルは背後のカインを振り向いた。なぜか薄っすらと笑みを浮かべている幼なじみを睨みつけると、今度は声を上げて笑い出す。なぜだ。
「ご飯たべたのにさ、カイン。
それ多分、甘い物が足りないんだよ」
あほか!
カインが抗議するより早く、セシルは間の抜けた笑い顔でポケットからクッキーを出してきた。
「お前、本当に……」
呆れてその後が続けられなかった。
セシルのポケットに、いつも何かしらの菓子が入っていることは知っている。菓子だけでなく、邪魔になるからいつでも纏められるようにと言う理由でヘアピン、ゴムに始まり、なぜか巻尺にクリップ、いつだったかポケットから調味料が出てきた時は、さすがに食堂に返して来いと叱ったことがある。
「あ、大丈夫。これ、今日の帰りに買ったから」
見当違いな保障を適当に述べて、はい、あーんとか言いながらクッキーを掲げて見せるセシル。
ああ、まだこいつ、俺が甘党だとか思ってるわけか。
胸中でひとりごちて、どうしたもんかとカインは半目で考える。
目の前でへらへら笑う幼なじみのクッキーを持った腕をとりあえず掴んだ。セシルは驚いたのか、少しだけ抵抗するように力が入ったのがわかる。怒っているわけではないと伝えるために、力を緩めてはやるが、ついでにクッキーは遠ざけておく。
不思議そうな視線を受け流しながら、当たり前のように、もうなんの緊張も沸かなくなってしまったセシルまでの距離に踏み込んでキスをする。
「…………」
慣れた二人のキスは、唇同士が触れると、勝手に始まって勝手に終わってしまう。そう感じてしまうのは、もう習慣として毎日繰り返されているから。計ったことはないけれど、きっと時間も決まってしまっているはず。
ただ、今日だけ違うことがあるとすれば。
『甘くない……』
キスの最後に、セシルの唇に残る菓子の甘さに辟易していたカインにとって新しい発見だった。
そうか。先に取り上げてしまえば良いのか。
カインはしめしめ、と内心ほくそ笑んでいたところ、離れた隙をついて口にクッキーを突っ込まれてしまう。
なぜか釈然としないものを感じながら、甘いはずのそれを、苦々しく噛み砕くのだった。
.
.
.
.
.
4 君からは近付いてきてくれている?
寝る時は、大抵どちらかのベッドで一緒に寝る。
子ども時代の癖が抜けないと言ってしまえば甘えだが、これももう、当たり前になってしまっている。喉が渇いたら水を飲むほどに。
結局課題を放り出してしまったカインは、少し落ち込んでいた様子だった。彼にとってすればたとえ学校の宿題であっても、課せられた責任と言う意味に等しい。己を偽る事を良しとしない性格を生真面目だの頑固だのと、セシルにさんざんからかわれたが、それもまた美徳だと自分を慰めることで落ち着いていた。なのに投げ出してしまった責任感が少なからず彼を苦しめたが、隣で毛布に埋まりながら幸せそうに笑う幼なじみを見ると、自分の悩みと言うものが取るに足らないもののように感じてしまうのだった。
「雨が降るのは嫌なんだけどさー。
雨の日にセールやるお店があるんだよねー、楽しみー」
だってこれだもんな。
寝入り端特有の、少し緩んだ口調に馬鹿馬鹿しくなったカインも枕に頭を埋める。布団の奪い合いをしなくてすむのは、二人がぴったり寄り添っているからだ。枕はどうしても二つ使うことになるが、二人で一つの毛布を使うのはとても効率が良いと思う。
一人で包まるより断然温かい。カインの平熱が低いからそう感じるだけではないはずだ。
「あー……寝そう」
今から寝もうとしているから不都合はないのに、セシルは唸り声を上げてカインに向き直る。
「カイン、じゃんけんー」
眠らないようにか、片手で眦を擦りながらもう片方の手を軽く振って勝負を促す。
『おやすみのキス』を始めたのがいつかははっきり覚えていない。
年端も行かない子どもの頃の他愛のないやり取りから始まったように思うが、それを言ってしまえばこれまでの習慣は全部そうだ。要は、セシルの提案にせよカインが言ったにせよ、もう一方がそれを了承した時から始まっている。
ごく当たり前の関係だが、二人の決まりごとは少なくはない。
いつもだったら面倒臭そうにしながらも、黙って勝負に応じてくれるカインだったが、なぜか今日はそうしてはくれなかった。
「………じゃんけん、しないの?」
眠さで胡乱だが、あくまでも習慣には拘るセシルの問いに、カインはさして興味なさそうに呟く。
「どうせするんだったら、勝負しなくても良くないか?」
「ん?」
回転の鈍った頭を捻って、セシルはカインの言葉を反芻した。
二人の間では『おやすみのキス』は、寝る前のじゃんけんに勝った方が先にできる。負けた方は負けたのだから、勝者にキスをする。となると、結局は往復キスになる。
「……うん? うん、そうだねぇ」
「なら、もうじゃんけん省いていいだろ」
事も無げの様子のカインに、セシルはぽかんと口を開けて間抜け面を晒す。
「えー……っと、いいの?」
「なんでだ?」
「……ううん。
じゃ、それで」
いつから『おやすみのキス』を始めたのかは覚えていない。けれど、始めたのは覚えている。セシルだ。
初めて『友達』とお泊りをした時に、嬉しさのあまりにやってしまったことだ。
それが、いつから習慣になってしまったのかは分からないけれど、真面目で固いカインを上手く誘導して(または仕向けて)、今では当たり前のことにしてしまっていた。始まりを覚えているセシルとしては、少なからず後ろめたさを感じていると言うのに。
「『おやすみ』、セシル」
拍子抜けしてしまった自分の先手を取って、カインが身を乗り出してキスを見舞う。
先手を取られたことに、あ! と思わなくもなかったが、子どもの頃の約束を律儀に守り続けてくれる幼なじみへの愛情を感じながら、すぐに自分も彼にキスをお返しして囁いた。
「『おやすみなさい』、カイン」
最後に簡単な抱擁をして枕に沈む。
きっと今日は、良い夢が見られるに違いないし、たとえ天気が雨でも、明日は良い日になるに決まっているのだ。と、セシルは期待せずにはいられなかった。
.
.
.
.
.
5 このくらいがちょうどいい
「まあ、こんなものだよね」
縁石に腰を下ろしたセシルの溜息には疲れと諦めが滲んでいたが、本人はさして残念がる風でもなかった。
「俺もお前も、運が良かった試しがなかったな」
「良く考えたらそうだよねー」
正直、シュークリームごときに運を使いたくはなかったカインだったが、朝の五時から並んで七時の開店まで粘って無収穫と言うのも納得が行かない気がする。
行き交うひとの波を眺めて、気付けば九時になる。そう言えば朝食も六時ごろに腹に収めたパン一つ。
それでなくとも、育ち盛りの青少年だ。腹も空いたと主張を始め出す。
「そろそろ帰るか」
カインは呟いて立ち上がり、尻の汚れを払う。しかし、セシルは気の抜けたような顔で雑踏を眺めたまま、動く気配すらない。
「腹減らないのか?」
「………お腹空いたー」
「減りすぎて動けないとか言ったらぶん殴るからな」
半眼で見下ろすと、難しい顔をして唸るセシル。
長い付き合いのお陰で、待たせても怒られない時間を計れるようになっているらしい。カインが限界を感じる手前で渋々腰を上げた後、小さな溜息とともに歩き出す。
どこかで食事しようかと言いだすこともなく、とぼとぼと言った足取りのセシルを横目で観察している内に、ああ、と思い当たることがあった。腹は確かに空いているが、少しの寄り道をするくらいの余裕はまだある。
俯きがちのセシルを誘導して大通りから少し離れると、バロンに良くある静かな裏道に出る。ひとの気配よりも物が多い場所で足を止めると、セシルはさすがに様子に気付いて辺りを見回した。
「? 帰るんじゃないの?」
「お前があんまりひどい顔してるからな」
指摘すると、むっと押し黙る。思った通りだったことに気を良くしたカインはポケットを探り、飴を取り出す。腹持ちのためと言って一袋持ち込んだセシルが、カインに一粒だけ押し付けた挙句、残りはすべて平らげてしまったものだ。
「糖分が足りないんだろ」
にやりと口角を上げて、自分の口に飴を放り込むと、不思議そうに瞬きをするセシルを掴まえて口付ける。
一瞬引きかけた身体は、手首を軽く握ると動かなくなった。最初から抵抗する気はなかっただろうが、セシルの気持ちに躊躇いを受け取ったカインは、ゆっくりと腕を回して抱き締める。
触れ合う唇が解けて、互いの呼吸を与えあう頃に、熱で溶け出した飴玉の甘さがじわりと広がり始めた。
いつもなら辟易する砂糖の甘さが、急に愛しいものに感じられて、カインは夢中で飴玉を転がす。最後には、二人の舌が奪い合うように絡み、唾液に混じって口の周りをベトベトと汚す特有の粘質の不快さも気にならなくなっていく。
「……っ」
息が上がるころに限界を感じたカインは、飴玉をセシルの口に押し込んで離れ、口元を拭った。しかし、このべとつきは水で洗わなければとれそうにもない。
「………」
呼吸を整えて、同じように不快そうに服の袖で口を拭うセシルがおかしくなって、何となく笑ってしまう。
「………なに?」
飴を含んだ口でもごもごと不満を訴える彼に、カインはお見通しなんだよ、と、もう一度笑った。
「お前が『一緒に』、って言うから来たんだ。いつでも、な。
だから――」
無駄骨折らせたなんて悔やむな。
その青い瞳には、何でも見透かしてしまわれるようで、セシルは顔を俯けた。
このひとの事は、本当にずっと大切なひとの一人だと思っている。けれど、こんな時は少しだけ憎たらしく思ってしまう。悔し紛れに噛み砕いた飴玉を飲み込んだら、次はこちらから不意打ちを食らわせてやろう。
今度は、彼が降参するまで離さない。
.
.
.
.
.
お題拝借こちらから → serenade