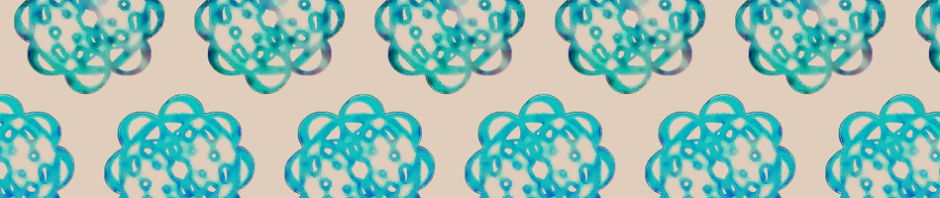彼はいつも誤解をされているひとだ。ただそれは、あまりにも彼を知らなすぎるひとと、彼を嫉むひと達の思い込みで、実際のところ彼は良く言われているような人物ではないし、風評を否定したり訂正することに必死になる類でもない。それが余計に彼のイメージを曲解させているのかもしれなかったが、前述の通り、彼は実に無頓着なひとだった。或いは、それこそが彼を示す端的な説明なのかも知れない。
その事実を悔しいとも悲しいとも思わないし、苛立ちも当てはまらなかったけれど、やはり幼馴染に対する誤った評価を聞かされるのは気分の良いものではなく、その時も、聞くとはなしに耳に入ってきた声に、ぼくは足を止めてしまった。
「だからあいつは気に食わないんだ。昔っから涼しい顔して、オレ達を見下してやがる、なあ?」
一学年上、つまり、カインの同級生だ。上のクラスの人間に詳しくないぼくでも知ってるのは、彼が明らかな「反カイン」を掲げているからだ。だから、その話題の中心が誰かなんて、周囲も気付いているし、ぼくも分かった。
「御実家が騎士の名門だか何だか知らないが、それだからって自分もお偉いんだと勘違いしてるのさ」
「いやいや、歴代の王に仕えてる家系だぜ? お貴族様には違いない」
「なるほど。血が青い、ってか」
取り巻きなのか、同級生数人は一斉に下品な笑い声を上げる。
その周囲でぼくの姿を見つけた他のひと達が微妙な戸惑いを感じたのが分かったが、彼らもその空気に気付いたようだった。ぼくを見た例の同級生はしまったと言うように目を見開いて、取り巻き達と小声で示し合わせながら慌てて逃げ出して行った。
何だかなと思っているうちに、一瞬だけ冷えた空気も再びもとのざわめきを取り戻す。
表立って反感を買うほどに、カインと言うひとは目立っている。多分、本人にその自覚はないのだろうが、少なくとも、彼の名前を出せば大概のひとは好意か敵意かの二種類の反応を示す。
敵意を感じているひとのほとんどは、あの同級生達や、彼らの悪口を真に受けているひとばかりで、逆に言うと、彼に直接何らかの害意を受けたと言うひとはいない。噂が一人歩きをしているだけだ。
そして好意を感じているひとは、彼の誠実さを良く知るひと。ぼく然り。
カインは常に誠実だ。嘘をつかない、誤魔化さない、努力をやめない、信じたことを諦めない、公平な判断をする。でもそれは『ひと』へのそれではない、彼は、『彼自身』に対して誠実なのだ。そして、他人からの評価はまるで気にしない。ひとを尊重しても、興味は薄いのかも知れない。だから、カインの誠実さから生まれた才能や技能だけを見て嫉妬するひとは、彼を冷たい人間だと揶揄する。
あのひとが、どんなに努力してるのかも知らないくせに。
段々と募ってきた苛立ちから逃げるように、ぼくは足を進めた。
図書館で借りた本は、カインから頼まれていたものも含めて四冊ある。この本に八つ当たりする前に、とりあえずさっさと教室に持って行ってしまいたい。そして、思い切り体を動かせば、このもやもやもすっきりしそうだから。
「あれ?」
早足で先を急ぐぼくは、ふと見下ろした窓の下にカインを見つけた。彼自身、前述した通りの性格なので華美は好まない。けれど、生まれ持った姿が彼をむやみやたらに派手に見せてしまう。それもまた、人の目を惹いて嫉まれる要因なのかも知れない。だから、あの金色の髪が太陽の光を反射してきらきらと輝いていることも、主張しているようにしか見えなかった。
学年すら違うカインが休憩時間をどう過ごしているかぼくは知らないけれど、少なくとも、中庭でぼんやりと過ごしているタイプのひとじゃない。早足を駆け足に変えて、ぼくは中庭に降りた。
休憩時間はまだたくさん残っているけれど、中庭に下りているのはカインだけで、ベンチに座ってこちらに背を向けている彼の周囲には、たくさんの防具が転がっていた。
「なに、してるの……?」
「……よお」
緩慢な動きで振り返るカインの手元には、足元と同じ類の防具と、雑巾。それを見てようやく彼が、備品の手入れをしていることに気付いた。彼と雑巾と言う組み合わせがあまり想像できないものだったから、直結するまでに時間がかかった。
ぼくが続きを継げずにいると、カインは素っ気無くもとの作業に戻る。
備品である防具は、どの学年もクラスも関係なく、使ったクラス内の持ち回り当番が手入れをすることになっている。だから、カインにだって公平に当番はやってくる。でも、備品はクラスの人数分あるものだから、大抵は数人で取り掛かるのが普通だ。でも、ここにいるのはカイン一人。
「カイン、一人?」
「そうだな、一人だな」
「それって、一人でやる仕事じゃないよね?」
「午後の課題で大忙しらしい」
「……押し付けられたの !?」
ぼくはびっくりしたのだけれども、カインはぼくの大声が気に入らなかったらしい。こちらを向いた顔には、明らかに不快そうな縦皺が眉間に刻まれていた。
「おい、俺を見くびるなよ。
勿論、先一月の昼飯は安泰だ」
「せっこいね」
呆れるぼくに対して彼の反応は単純なものだった。再び黙々と手を動かす。それだけ。
だから何となく離れがたくなって、ぼくはベンチの隣に腰掛ける。彼は相変わらず手元に集中していて――或いはぼくの挙動に頓着をしていないか――こちらを窺おうとする気配すら見せない。
ぼくも彼から視線を逸らして、空を見上げる。膝に乗せた本の角を揃えながら、建物の端に辛うじて引っ掛かった太陽を探した。聞こえる音は、辛抱強く往復する雑巾の衣擦れのものだけ。
「さっき、食堂で何か言われてたよ」
のんびりとした空気だったからなのか、ぼくはうっかり吐き出してしまった。カインはぼくの声の調子から、それがどんな意味を持っているのか気付いているはずなのに、嫌そうに眉を顰めることもぼくを諌めることもせずに、小さく鼻を鳴らした。本人が陰口を知っているなんて皮肉なことだけれど、つまり謂れなき彼の悪評は広まっている。それでも尚、公然と『陰口を囁く』人物の名も、そこまでになればカインは知っている。だから、彼は鼻を鳴らして笑ったのだろう。
「態度がデカいとか、教師に媚売ってるとか、冷血漢だとかだろ」
「血が青いとかも言ってたよ」
ふと、カインが手を止めた。不思議に思って見れば、思案顔で何やら考えていたのだけれど、一人合点のように頷いて、作業を再開する。そして、ぼくの疑問に被せるように彼はぽつりと一言呟いた。
「それなら、あと三つで良いな」
………みっつ、?
「…………何が?」
「サムシング・フォー」
……………………
「カイン……お嫁さんに行くの?」
再び手を止めたカインはぼくを見た。さぞかし、間抜けな顔をしていることだろう。
交わした会話を反芻してでもいたのか、しばし首を傾げていた彼の中で何らかの結果が出た。
「変だな」
「……だよね」
けれど、溜息とともに吐き出したぼくの同意もカインにとっては展開に値しなかった。小さく首を竦めただけで、また作業に戻る横顔を見ると、このひとのこう言うところが誤解を招いてる所以なのだと思い知る。
カインは誤解されやすいひとだ。
決して高慢でも冷徹でも、血が青いわけでもなくて、彼は常に自分に誠実であるだけだ。そしてそれ以外のことには、あまり興味を示さない。それが彼の評価を誤らせている一因で、実のところ、彼は本当は誰よりも暢気なひとなのかも知れないね。
―――――――――――――
労働を知らない貴族の肌は白く、静脈が青く透けて見えたと言う皮肉から貴族を
ブルーブラッドと呼んだと言う説もあるそうな。
サムシング・フォー = 「四つの何か」を身に着けたお嫁さんは幸せになれる、欧米のおまじない。