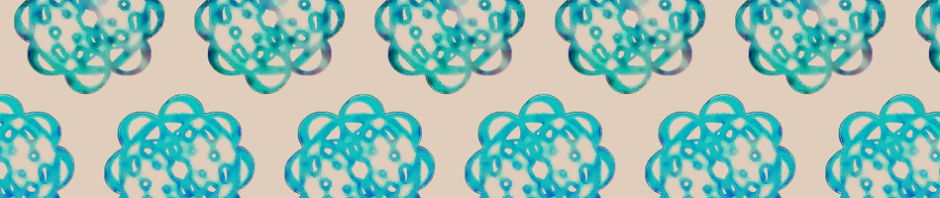吐息を、吐く。
今年も例年になく、規律の厳しさに、一週間で三分の一の学生がリタイアしたと噂されるバロン衛兵学校だけあって、自堕落を好まない彼にとっては良い環境だと言えた。
学業も同じくらい厳粛で、怠惰に過ごす時間が実に少ない。
寮住まいと言え、最低限自分のことは自分で面倒を見るのは彼の最も好むところでもあったし、己への責務としてはその程度の方が生温くなくて良い。
学舎でも寮でも区別なく同じような時間の過ごし方に悲鳴を上げる者も少なくなかったが、違いをひとつあげろと言われれば、寮は寝るところだと答える岩のような面白みのない、彼を含めた向上心に貪欲な生徒だけが切磋琢磨して、堅固な岩のような兵士になり、やがてバロンの城壁を守るのだ。
だがそれも仕方ない。
王を守る城壁は、岩より堅くならなければならないのだから。
その日は朝から白兵戦の訓練。トーナメント形式の模擬試合が行われていた。
生徒の数の関係で、三日の日程、それぞれ四時間程度で切り上げられる。
噂によると、次学期のクラス選考も兼ねているとの話で、否が応にも気合は入る。
今日の試合で勝てたカインは、相手に恵まれていたのだと、決して己を奢ることもなく、一人で黙々とトレーニングをしていた。それも明日に備えて、小一時間ほどで切り上げ、放り投げるように上着を脱いで、手短に着替えていたロッカー室で。
カタン。
小さな物音に、緩く反応する。
時間は三時を少し回ったころ。
冬のさなか、小春日和の暖かさがロッカー室を満たしていて、それまで身体を動かしていたカインには少々蒸し暑くすら感じていた。
「?」
ネズミか何かかとも思いながら、物音のしたロッカーの陰を覗き見るとそこに、ロッカーに凭れるように。
「セシル?」
幼馴染が、いた。
「おい、セシル?」
歩み寄り、床に座り込んでロッカーに身を預けるセシルの肩に手を重ねる。
乱れた薄栗色の髪は柔らかく、昼下がりの陽の光を受けてきらきらと輝いていた。
白っぽい肌は心なしか生気が感じられず、静かな深い呼吸と閉ざされた眼差し。
眠っている、と言うには様子が尋常ではないように思える。
「セシル」
呼びかけ、軽く肩を揺すってやる。
「ん……」
呼びかけが届いたか、薄っすらと開く瞳は翡翠の色に濁っていた。
「セシル?」
もう一度、呼ぶ。
「……ッ!」
肩を、軽く押すと、弾けるように身体が反応した。
びくりと、震えるように、脅えるように。
はっきりと開いた眼差しには、緊張の色がありありと見て取れた。
「…………カイ………ン?」
緩い瞬きの後、濁っていた眼差しに光が差し込む。
「こんな所でどうした」
そう問われ、しばらく躊躇っているように見えるのは、まだ眠いだけなのかも知れなかった。
ややあって、セシルは頷くように顔を下向けながら答えた。
「ちょっと、ウトウトしてて……」
『またこいつは……』 内心で呟き、腕を伸ばしたカインは、ロッカーに背を預けたままぴくりとも動かない幼馴染の手を取る。
セシルは驚いたように瞳を見開いた。
抵抗はしなかったが、彼に緊張が走ったのは確実で、それは強張った表情から窺がえた。
僅かながら腕に力が込められていて、それが一体何に対してなのか考える。
ほんの一瞬間の交錯ののちに、触れる指の熱さに気付いた。
「おまえ、少し熱くないか?」
「ね、寝てたからだと、思うけど……」
ぴくんと、震えるように跳ね上がった指が、言葉に反してカインの問いを肯定づけていた。
カインが渋面を浮かべて嘆息を吐くと、怯えたような色を浮かべて、セシルは口許を引き締めた。
もう片方の手も伸ばして、両の手で手首を握って逃げられないように捕まえると、相手は困惑の色濃い眼差しで無言の問いかけをしてくる。
カインが黙ったまま睨み返すと、すぐに、萎縮してか僅かに顔を俯かせた。
だがそれも許さず、相手を上向かせるように顔を近付けて額と額を擦り合せると、物言いたげな困った表情の幼馴染。
そう言う態度が全てを物語っていると言うのに、セシルと言えば、自分に悟られないようにしているつもりでいる。基本的に鈍臭いのだ、この幼馴染は。
触れる額が明らかに熱を持っていることを確信して、カインは頭を離した。
相手は、この十数年付き合い続けた息の長い幼馴染だ。
とりあえず、いきなり彼を振り切って逃げ出す危険はないと思うが(どうせ寮の部屋も同じなのだし逃げても意味はないことは分かりきっている)牽制のために、掴んだ両手首はまだ離さないでおく。
「いつからなんだ。
まさか朝からじゃないだろうな?」
「……えと、だから……大丈夫。
ちょっと疲れたから寝てただけで、別に 」
言い募ろうとするセシルにカインが一瞥をくれると、彼はぱっと口を噤んだ。
視線ひとつで機嫌を推し量れるようになったのは、長年の経験の賜物である。
聞こえよがしな溜息を、カインはもう一度吐く。
それから上目遣いにこちらを窺がっているセシルに、一転して柔らかな笑顔を見せて、
「そうか。疲れてただけか」
独り言のように呟く。
それに力を受けてか、とりあえず安堵したからか、どちらにしろ熱の制で折角の長年の経験もやや翳っているようで、セシルはほっと緩めた表情で、うんうんと頷いて見せた。
「うん。大丈夫、ちょっと疲れてただけだから」
「ローザにチクるぞ」
「ごめんなさいうそつきました熱がありますそれだけは!」
慌てて頭を下げて謝るセシルを見ながら、カインは呆れて怒る気にもならない。
二人のもう一人の幼馴染、ローザの名を出すと、セシルは簡単に口を割る。
もう、かなり前から気付いていたが、彼がローザと距離を置きたがっているらしいことには知らない振りをしていた。多分に、カインの想像に難くない事情があることは明らかで、だからこそ正直、あまり使いたくなかったのだが、ぐずりだすと長くなるので致し方あるまい。
捕まえていた手首を離して改めて手の平を額に当てて熱を測ると、思っていたよりも高かった。
「朝から悪かったのか?」
問いには首を横に振る。
模擬試合が終わった辺りから熱っぽさに気付いて、少し休むつもりがうっかりそのまま転寝をして、今に至ると言うのだ。
そのあまりの情けなさに、カインは怒鳴るとか殴るを通り越して頭が痛くなってくる。
鈍臭い鈍臭いとばかり思っていたが、ここまでくるともはやのろまだ。
よくもまぁこの年齢まで無事に生きてこられたものだと、むしろ感心すらしてしまう自分を、不思議そうに見つめてくるセシルの目はどこか虚ろだった。
押し問答を始める気にならず、嘆息を漏らして、帰り支度を始める。
「荷物、中か?」
自分の荷物を適当に纏める間に、セシルはふらふらと不安定な頭を持ち上げて、うんとだけ答えた。
グズでノロマな幼馴染は我慢強い。我慢強く、少々のことでは音を上げない。
それはどうも性格だけではなく、ひととしての構造上、もうそう言う風にできているのか、痛みに対しても我慢が利くのだと思っていたのは、実は痛覚とかの神経が二、三本くらい繋がっていないせいだけだったのかも知れないとまで思い始める。
セシルに限っては、それも冗談にもならないような気がするのはなぜだろう。
彼のロッカーを見つけて、適当に中のものを取り出して自分のものと一緒くたに纏めていると、のろのろと立ち上がったセシルが近寄ってくる。
「良いからおまえ、少し待ってろ」
「……でも」
そうこう言う間も足元はふらついて、今にも倒れそうな様子が危なっかしいことこの上ないので、ロッカーの扉を響かないように閉めて、急いで彼の腕を掴んでおく。
それから腕に引っ掛けていた上着を抜いて、ロッカー側に凭れだしたセシルの肩にかけた。
「これ、」
「着てろ」
短く告げると、セシルはその声の厳しさに長年の経験で何かを察知したらしく、怒鳴り声が飛ぶ前にもそもそ袖を通した。だがどう見ても、寮まで歩いて行けるような状態ではない。
瞑目して嘆息を漏らしてから目を開けると、上着を着込んだセシルは、こちらが黙っていることに少なからず緊張していた。
しょうがないな。
カインは肩にかけた荷物を身体の前面に回して、掴んだままのセシルの腕を引っ張り、荷物のように彼を背中に担ぐと、慌てて悲鳴が上がった。
「カイン!」
「いいから大人しくしてろ」
「………でもっ」
「まだちょっと足りないけどな、良い重石になる」
幼馴染の負ぶさる背中が熱い。
夏の暑さで落ちた体重も元に戻ったらしいが、それでも平均に足りないセシルをおんぶしたカインがロッカーから出る頃に、首元で感じた吐息が、ありがとうと聞こえたのは気の制ではないだろう。
病気に対しても痛みに対しても割合頑丈に出来ているセシルは、なぜか新月の夜に調子を崩すことが多かったが、身体のつくりが安定する頃には落ち着いた。
それでも、こんな風に体調の思わしくない時期に新月が重なると、同じ度合いの風邪でも怪我でも治りが遅くなることをカインは知っていた。
どうしてなのかは分からないが、悪化するにしろ沈静化するにしろ、それが月の出ている夜に深く関わっているらしいことを長い付き合いで学んだことは確かだった。
今日は半月だった、と、カーテンの隙間から覗く星空には雲もない。
あれから結局、寮に着くころに背中で寝入っていたセシルを、起こさないようにベッドに移し、寮母に頼んで病人食を用意してもらったカインは、その傍らに寄せた椅子に腰掛けている。
課題が出されているわけでもなく、特にやることもないので看病の真似事をしていた。
「……………あ、れ………?」
掠れた声が聞こえて、手元の本から視線を移すと、セシルが頭だけを起こして焦点の定まらぬ目でいずこかを見ていた。
「起きれるか?」
聞くが、相手はあーだのうーだの呻き声を発して、未だ目覚めていない様子。
手を伸ばして額に触れて熱を測るが、どうも昼間より高くなっているような気がする。
「冷たくて、きもち、い?……」
「お前が熱いんだ。待ってろ」
指で額を弾くと、小さな悲鳴が上がった。
水を張った洗面器に浸したタオルを絞って、デコピンで赤くなった額に乗せてやると、ありがとうと小さく呟くのが聞こえた。
「何か飲むか?」
ベッドの端から腰を浮かせながら問うカインだったが、セシルは何とも言えない表情で小さく首を振る。
「あの、カイン………」
その先を躊躇う態度に、再びベッドの端に腰掛けて耳を傾ける。
「……ローザに、は、」
無意識に溜息が漏れそうになるのを、危うく呑み込んだ。
セシルは孤児であることを理由に、幼い頃からからかわれることもいじめられることも多かったが、そんなセシルにとって、カインとローザだけは何の隔たりもない友人で、それは今も昔も変わることはないと彼は思っていた。
だが、年を重ねるごとに逞しく成長するカイン、美しくなるばかりのローザ。
それに比べて、どこの誰とも知れぬ、よそ者の自分。
もう、三人一括りで扱われるような子供ではなくなった頃から、セシルは言われなれた中傷が波及することを恐れ、二人との接触を避け始めた。
事情を暗に汲み取ったカインはともかく、困惑するばかりのローザは余計にセシルに構いたがり、結果、少しの怪我や風邪でも大袈裟に騒ぎ立てることが多くなった。
それも手伝って、セシルは、ローザに不調を悟られることを何よりも恐れた。
「ああ。言わないでおいてやる」
安心させるようにタオル越しに額に触れてやると、安堵したのか、口許を緩めて見せる。
「言わないでおいてやるから、明日はここで大人しくしてるんだな」
にやりと笑みを浮かべると、セシルは口を尖らせる。
「あー……折角今日、頑張って勝ち残ったのになー」
「ま、この次はせいぜい体調管理もしっかりやることだな。
優勝メダルは土産に持って帰って来てやるから、明日は大人しく寝て、風邪治しとけよ」
「………くやしーなー」
恨めしげに見上げてくるセシルの顔はどこか間が抜けていて、カインの笑いを誘った。
子供にするように布団を撫で付けてあやしてやると、どこか白けた表情を浮かべるセシルの瞳に、開け放したカーテンから覗いた半月が、ちかりと閃いた。